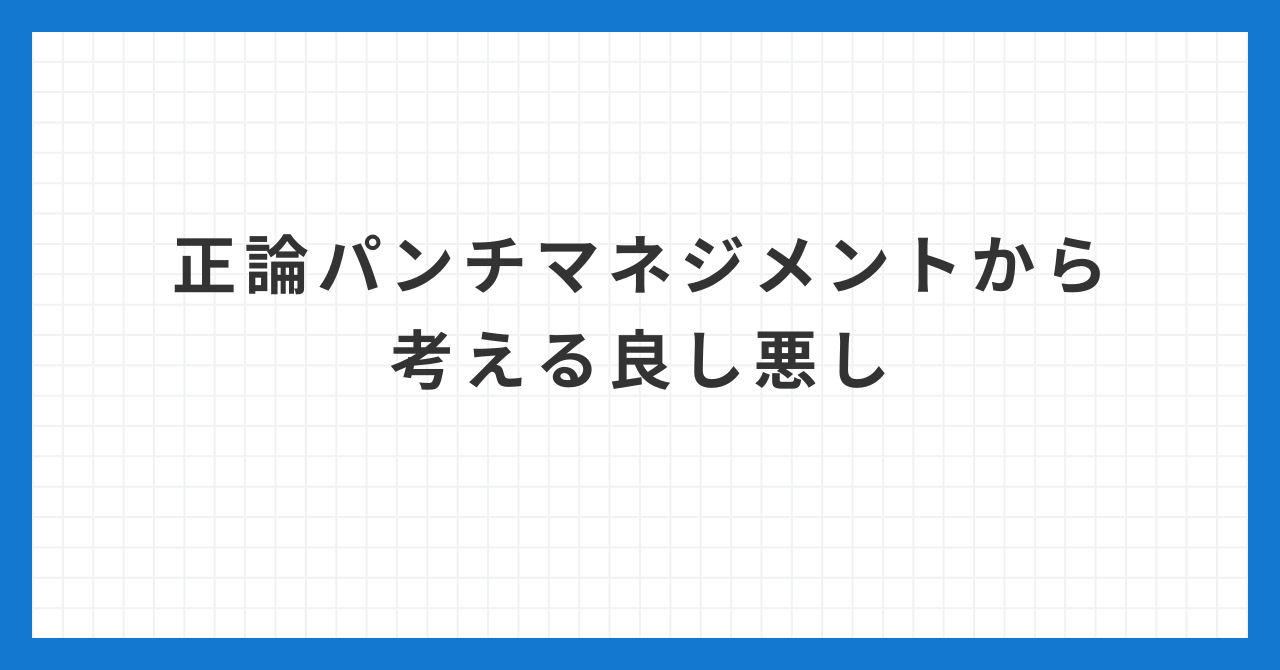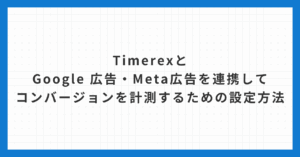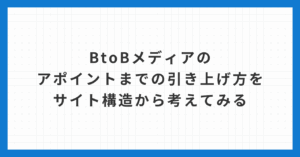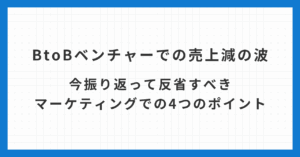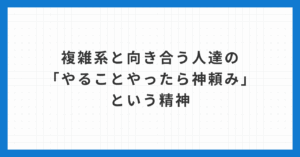正論パンチマネジメント
正論パンチマネジメントとは、フィードバック等の際に論理的に正しいとされることを軸に、感情に寄り添うことなく淡々と詰めていくマネジメント手法です。(造語)
受ける側としては相手の言っていることは正しいとされることなので反論の余地はほぼなく、淡々と詰められ続けることになります。
フィードバックとしては正解なのかもしれませんが、マネジメント的には長期間同じようなことを続けると、大体部下が潰れてしまいます。上長は正しいことを言い続ければいいだけなので、運用は楽という特徴があります。
マネジメント・フィードバックの構造
マネジメントの基本構造は以下で成り立っていると考えます。
- 上長が思う論理的に正しいと思うことを伝える(考え方・理論・答え等)
- 上長の論理(考え方・理論・答え等)を心底から納得し、自分のものとして落とし込んでもらい実行してもらう
上記を満たすためのありがちな2つのメーターは以下があると思います。
- 論理 :「論理」の部分なので当たり前のように重要
- 感情: 「納得」「落とし込んでもらう」は、相手に動いてもらわないと実現できないことなので重要
マネジメントスタイルの2つのメーター
正論パンチマネジメント(論理:5・感情:1)
論理は正しいものの、感情に寄り添わないため、マネジメントされている側はひたすら正論で殴り続けられる感覚になり、潰れやすい傾向があります。対象によって変化する感情に寄り添わなくていいので、マネジメント側としては一律的に論理でマネジメントできるため楽です。これは「一律型マネジメント」とも分類できます。
寄り添い論理マネジメント(論理:5・感情:5)
論理を用いて相手が受け入れやすいように感情に寄り添ってマネジメントします。対象によって変化する感情に個別的に寄り添ってフィードバックするので、マネジメント側の負担は結構あります。手塩にかけてフィードバックしても、その分がすぐ絶対に伸びるわけではないので、メンタルにくるときもあります。これは「個別型マネジメント」とも分類できます。
「論理」部分は変化する
感情部分は変わらないものの、論理部分は時代・人によって変わってきた部分もあります。
- 「論理」じゃなくて「恐怖」 → 恐怖マネジメント
- 「論理」じゃなくて「暴力」 → 体罰マネジメント
- 「論理」じゃなくて「権威」 → 後光マネジメント(※権威性がありすぎて、その人のフィードバックが全て正になってしまう)
これらはグラデーションなので、上記はかなり極端な例といえます。これらも「一律型マネジメント」に分類されます。
寄り添いマネジメントの現実
昔は寄り添えばいいと思っていましたが、今は寄り添い続ければいいというものでもない気がしています。それは、マネジメント側の負担が思っているよりも大きいからです。
マネジメント層は基本的にプレイヤーも兼任している人が多い中で、多人数に対して寄り添い型のマネジメントをするのは、結構な心のリソースを消費します。(もちろんマネジメントする人の特性にもよるし、全てこなしてしまうスーパーな人もいます)
そのような中で「一律型マネジメント」は、マネジメント側の消費リソースを少なくしてくれるという点で機能することもあります。
組織状況による選択すべきマネジメントの違い
応募者が多い(補充ができる)場合
一律型マネジメントで、そのマネジメントが合わなければ辞めていく、チーム移動などで生き残った人のみがマネジメント成功となります。
応募者が少ない(補充ができない)場合
辞められると困るということもあり、個別型マネジメントで感情に寄り添いながらマネジメントしていく必要があります。
ほとんどの中小企業は、バンバン人を採用できる費用面含めたリソースはないのではないでしょうか。そうなると必然的に個別型マネジメントを選択せざるを得ないと思います。
個別型マネジメントの負担を下げるための考察
1. 見る人数を絞る
個別型マネジメントを実施するのであれば、スーパープレイヤー以外は3〜5人くらいが限界だと思っています。この人数も例えば3人とも業務含めた指導リソースを多く使わなければいけない形であれば、それが限界である可能性もあります。このキャパは人それぞれだと思うので認識しておくことが大事です。
2. 採用をちゃんとやる
採用が一番のマネジメントだと思う節があります。マネジメント側との相性や相手の特性、職業特性・組織カルチャー・組織で求められることとの乖離がないかなど、入ってからのマネジメントを頑張るよりも、ここでしっかりと組織やマネジメント側と合致しやすい人物を採用できるように頑張る方が再現性が高いと考えています。
以上、正論パンチマネジメントの記事でした。